ヤリキレナイ川の由来について、動画を作成してみました。以前作成した記事を元に、解説動画として再編成したものになっています。
原稿書き起こし
①
ヤリキレナイ川って地名、聞いたことがありますか?
こんにちは、東北きりたんがお送りする、蝦夷島紀行の時間です。
ヤリキレナイ川は北海道の由仁町を流れる、とても小さな川です。でもトリビアの泉など、テレビで何度か取り上げられたこともあって、北海道の面白地名としては結構有名な方ですよね。
ヤリキレナイ川は「川」を表す「ナイ」が付いていますから、アイヌ語地名らしくも聞こえます。でもこの意味がちゃんと解釈されていないんです。看板に書かれた由来は正しくないかもしれません。
ということで、まず現在はヤリキレナイ川がどう解釈されているか見てみましょう。
現地に行くとこんな看板があります。
アイヌ語河川名「ヤンケ・ナイ」又は「イヤル・キナイ」
意味「魚の住まない川」又は「片割れの川」
どうでしょう。既に解釈が2つに割れていますね。どっちが正しいのでしょうか?残念ながらどっちも正しくありません。
②
まず「ヤンケ・ナイ」。これは残念ながら全然違います。
「ヤンケ」に「魚の住まない」という意味はありません。アイヌ語地名の「ヤンケ」というのは「レブン」の対義語にあたり、「陸の方の」という意味です。レブンが「沖の方の」という意味ですからそれの対になっているんですね。島や岬など海沿いでよく出てくる地名です。
ですから「ヤンケ・ナイ」の正しい意味は「陸側の川」ということになり、「魚が住まない」なんてのはもう、元の意味にかすりすらしてません。それにヤンケナイとヤリキレナイは音が全然違いますから、この説は正しいとは言い難いでしょう。
③
もうひとつの「イヤル・キナイ」で「片割れの川」という説。
幕末に松浦武四郎の書いた地図に「イヤルキナイ」とありますから、そこから取ったのでしょう。、ですが「片割れの川」と解釈するとなると「イヤル・キナイ」と中黒の点の入れ方がおかしいんですよね。「イ・アラケ」で「その片割れ」という意味ですから、「イ・アラケ・ナイ」で「その片割れの川」。「イヤル・キナイ」とそこで中黒を入れた人は全く意味を理解していなかったことになります。それにしても「アラケ」と「アルキ」、似ているようで微妙に音が違いますね。「ヤンケナイ」よりはずっとマシですが。
④
ではヤリキレナイ川の正しい解釈をしていきましょう。
正しくは「イヤリキレナイ」で「それらが来る川」です。
そう、イヤリキレナイです。定説では、アイヌ語ではもともとヤンゲナイで、川が何度も氾濫するから住民がもうやり切れないなぁということでヤリキレナイ川と訛ったということになっていますが、そもそも最初からアイヌ語の時点で「ヤリキレナイ」なんですね。これは文法的にも正しいです。
細かく見ていきましょう。
まず「ナイ」は川、もしくは沢のことです。
「アリキ」は「来る」という意味の自動詞の複数形です。アイヌ語は名詞ではなく動詞を複数形にすることでたくさんを表すんですよね。
釧路に「阿歴内川」という川があって、これは「アリキ・ナイ」で「たくさん来る川」の意味ですね。
この「アリキ」に「レ」という接尾語をくっつけることで、自動詞を他動詞化し、使役の意味を持たせます。つまりは「アリキレ」にするとこで、名詞を前後に合計2つ持てるようになるということです。それで前に「イ」後ろに「ナイ」を置いた、「イ・アリキレ・ナイ」という形が出てくるわけですね。アイヌ語地名は「イ」と「ア」が連続すると「ヤ」に化けるという法則がありますから「イ・アリキレ・ナイ」は「ヤリキレナイ」と発音されます。無事ヤリキレナイの形が出てきました。
⑤
では先頭の「イ」は何を意味しているのでしょうか?イは「それ」という意味の形式名詞ですから、それが何を指しているのかはっきりと断定することはできません。ですが地名の場合、このイは熊を指していることが多いです。熊のような恐るべき存在を、あえてその名で呼ばないんですね。これは忌み言葉という習慣です。うっかり名前を呼んでしまったら本物が実際に来てしまうので、呼ぶのを避けるのです。
ですから「イ・アリキレ・ナイ」は「熊たちがやって来る川」と解釈していいでしょう。あえて忌み言葉に倣うなら「奴らがやって来る川」です。
ところで「イヨマンテ」という言葉をご存知でしょうか?熊送りという、アイヌの信仰上1番重要な儀式になっています。イヨマンテは「イ・オマンテ」で「それを・送る」の意味です。この「イ・オマンテ」と「イ・アリキレ」は「それを送る」「それらが来る」と反対の意味になっているわけですね。
⑥
ヤリキレナイと似た意味の地名として、小樽運河のところにイロナイ川があります。これは「イ・ル・ウン・ナイ」で「熊の足跡がある川」と解釈されます。ここでもイは熊を指すんですね。実は間宮林蔵の地図では、ヤリキレナイ川が「イルベツ」と別名で書かれています。イロナイと同じ、「熊の足跡の川」ということですね。やはりこの辺りは熊が沢山いたのでしょう。
現在の馬追の丘はそこまで熊が多い場所という印象はないですが、地元のお年寄りの方によると「わしらが小さい頃は、馬追にはヒグマがいるから子供だけで遊びに入ったらいかん」、と言われていたそうですから、昔はもっとたくさんいたのでしょう。実は馬追の丘の北東斜面にもうひとつ「ヤリキリナイ川」があります。ここからすると、例のヤリキレナイ川に限らず、この辺り一帯が熊の出現地帯だったのでしょう。
由仁町の意味は一説では「イ・ウン・イ」すなわち「ユニ」で「熊のいる所」とも解釈できます。「ユンニ」で「温泉ある所」という説も捨てがたいですが、ヤリキレナイから熊が下りてきたということは、麓の由仁にもたくさん熊が来たのかもしれません。
⑦
アイヌ時代は現在の由仁駅前ではなく、駅から南東に5kmほど行った由仁町岩内地区にコタンがありました。コロポックル男性とアイヌ女性の間に生まれたカルベチシカリという女性が、この集落に嫁いだことによって、上ユウバリアイヌの祖先となったそうです。ユニやヤリキレナイの位置は、アイヌたちが住んでいた集落からはだいぶ離れていて、その辺は熊に要注意な場所だったというわけですね。
まとめると、ヤリキレナイ川は「熊がやってくる川」の意味で、ヤンゲナイというアイヌ語が訛ったわけではなく、最初からヤリキレナイというアイヌ語だったということになります。
最近は熊の被害のニュースがたくさん流れていますので、現地を訪れる際は、十分に周りを警戒しながら訪問するといいでしょう。
ご試聴ありがとうございました。
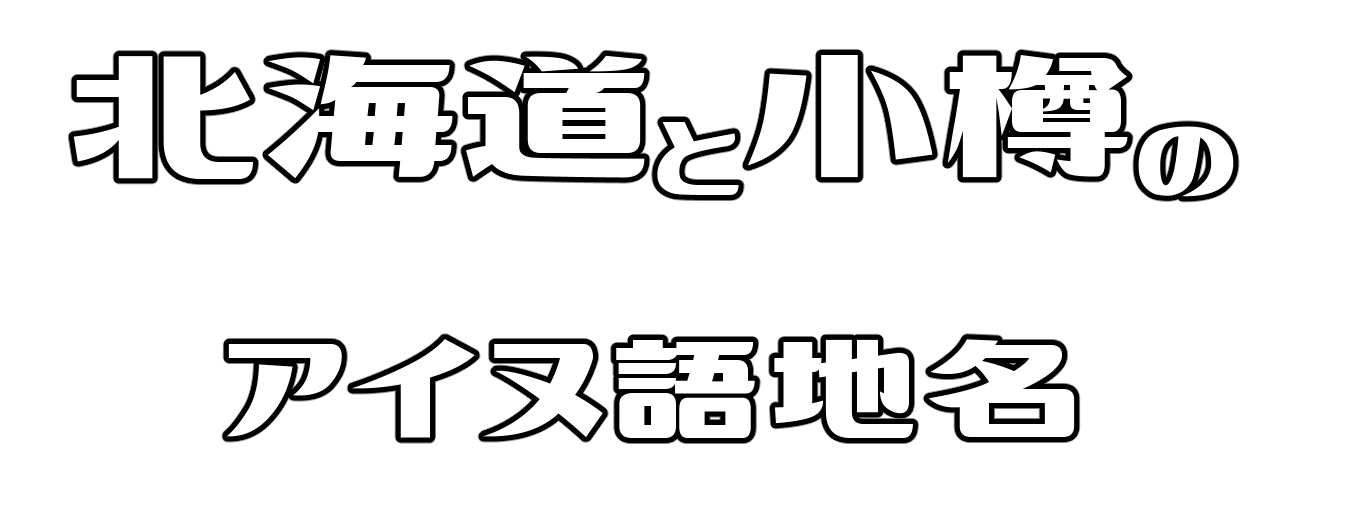



コメント