アイヌ語地名解の年代区分
北海道のアイヌ語地名を日本語の意味に訳そうとする試みは、江戸時代から今にかけて繰り返し行われてきた。その上で重要となるのはどの年代のものかということである。古ければ古いほど、当時のアイヌの生の声を反映したものである可能性が高い。一方、アイヌ語の文法的な研究などは年々進んできており、古い地名解が見直されていく傾向もある。
そこで便宜上、地名解を四つの時代区分に分けてみることにした。アイヌ語地名の由来を見かけた時は、まずそれがどの世代に唱えられたものなのかを考える必要があるだろう。
第一世代(江戸)
該当者:松浦武四郎、上原熊次郎など
この時代は、直接現地に住むアイヌに聞き取ることができた、貴重な時代である。
蝦夷地全体を網羅したものは松浦武四郎と上原熊次郎の書しかないが、他にも江戸時代の日誌等の中に稀に触れられることがある。この時代の地名解を第一世代としよう。
現地アイヌから聞いたからと言ってそれが必ずしも正解とは限らないが、それを否定できるだけの明確な根拠が無い限りはこの時代の説は覆すのがなかなか難しいのも事実である。当時の人がそう言っていたのだ。辞書を開いて適当に音が似ているものを見つけたから当て推量で、くらいの根拠では覆せない。
上原熊次郎
上原熊次郎はアイヌ語通詞(通訳)であり、文政9(1824)年に『松前并東西蝦夷地場所所々地名荒増和解』別名『蝦夷地名考并里程記』、通称『上原解』を書いた人物で、これはアイヌ語地名解の祖とも言える貴重な文書である。(原著→蝦夷地名考並里程記/東京国立図書館)。また活字化したものが『アイヌ語地名資料集成』に収録されている。
小樽の地名に関しては、ヲタルナイ、ハルイシ、クッタルシ、テミヤ、タカシマ、シクズシ、ヲショロについて触れている。
松浦武四郎
松浦武四郎については改めて説明するまでもないが、六度の蝦夷地探検の際に、詳細な日誌を残し、その中でたびたび地名の意味を書き留めている。北海道の名付け親とも言われる。
小樽は少なくとも三度訪れているが(銭函を含めると六度)、一度目(弘化三年)の旅は『再航蝦夷日誌』、二度目(安政三年)は『竹四郎廻浦日記』に記されている。三度目(安政四年)『丁巳日誌』は残念ながら通過しただけで小樽に関してはほとんど記録がない。これらをまとめて編集した紀行本『西蝦夷日誌四編』も参考になる(原著→西蝦夷日誌四編/国立国会図書館)。地名考をまとめたものとしては『蝦夷地名奈留辺志』がある。
第二世代(明治)
該当者:永田方正、白野夏雲、J・バチェラーなど
明治20年前後。アイヌ語地名研究の始まりの時代とも言える。特に『永田地名解』に関しては、今でも多くの箇所で引用されており、アイヌ語地名解の底本とも言える書である。
急速な和人化政策により生のアイヌ語を話すコタンはほぼ無くなっていたが、まだアイヌ古老が生きていた時代であり、彼らへの聞き取りによって得られた情報は貴重である。
ただ非常に槍玉に上がりやすいのも確かで、永田地名解は繰り返し批評の対象になってきた。批評される永田地名解はまだいい方で、白野やバチェラーの解はそもそも相手にもされないことも多い。
永田方正
明治24年に『北海道蝦夷語地名解』、通称『永田地名解』を著した人物で、多くのアイヌ語地名解はこの書をベースとしている。全道6000箇所もの地名の意味と発音を解説しており、その情報量は膨大である。アイヌ語をアルファベット表記で記すようにしたのも画期的だ。
しかし多くの批判に晒されてきたのも事実で、特に文法的な部分では誤りが多い。しかし、アイヌ語地名解を考えるならまずはこれを参照すべき。というほどの非常に重要な書となっている。
アイヌ古老からの聞き取りも行っており、小樽に関しては琴似又一(エカシ)から聞き取った情報が多いようだ。そして「妄称ナリ」「最モ誤ル」「甚シキ虚言ナリト」など松浦武四郎の説を痛烈に批判する論調がしばしば見えるのが面白い。
白野夏雲
明治20年に『蝦夷地名録』を著す。通称『白野解』。
小樽に関しては40ほどの地名を取り上げており、その訳を簡潔に記している。一般的な地名は永田地名解などとだいたい一致しているものの、非常に独特な解釈をしているものもあり、例えば朝里は「山中アサリ貝の殻を出す」、勝納は「ヘカチヘシナイで小児」などとしており、これらの独自解釈が参照されることは少ない。
J・バチェラー
イギリス人宣教師。『アイヌ語地名考(Ainu Place-Names Considered)』を著す。通称『バチェラー解』。
興味深い書だが、似たような音の単語をただ当てはめているだけという感じがある。知里真志保氏は「バチラーさんにしても、永田方正さんにしても、開拓者としての功績はまことに偉大なものがあるのでありますが、進んだ今のアイヌ語学の目から見れば、もうその人たちの著書は、欠陥だらけで、満身創痍、辛うじて余喘を保っているにすぎない程度のものなのであります。」(『アイヌ語学』知里真志保)と痛烈に批判している。
小樽に関しては蘭島、忍路、高島、手宮、朝里、銭函、小樽内について解を述べているが、例えばオタルナイを「ハマナス」としたのは氏の解である。朝里は「開いた場所」、手宮は「輪の陸地」、蘭島は「裸の石」など、かなり独自解釈が強く、これらの解はほとんど相手にされることはない。
第三世代(昭和)
該当者:知里真志保、山田秀三、更科源蔵、榊原正文など
アイヌ語の文法的な理解が進み、アイヌ語地名研究が本格的に行われるようになった時代。知里真志保・山田秀三両氏の著作は多くの地名研究家の手引書となってきた。『北海道駅名の起源』や各地の河川標識など、地名の由来が一般にも広く紹介し始めるようになる。
当時を生きたアイヌは居なくなってしまったが、明治初期を知る古老から聞き取る機会がまだ残されていた時代でもある。
知里真志保
アイヌにルーツを持つアイヌ語言語学者で、とくに地名に関する情熱が深い。既存の地名解をときに痛烈に批判しつつも、その著作の中で丁寧にその文法と発音について説明している。
知里真志保氏の『地名アイヌ語小辞典』は全てのアイヌ語地名研究者が携行すべき必須の本となっており、とりあえずこの辞典を紐解きながら考えるのが基本になっている。
小樽の地名に関しては特別にページを割いて書いたことはないが、祝津を「全く崖の多い所」としたり、手宮がテムムンヤではなく「テムィヤ」であることを説明したりなど、その書から学ぶべきところはたくさんある。
山田秀三
アイヌ語地名研究といえば最初に名前が上がるのが、この山田秀三氏である。氏の命日である7/28は「地名の日」とされている。わかりやすく丁寧に地名を解説した山田氏の本は、どの図書館にも必ずと言っていいほど所蔵されている。
実際にその土地を訪れて地形を確かめながらレポートする地名研究のスタイルは「山田式」とも言われ、その後の研究者達にも多くの影響を与えてきた。一方で、既存の地名解を大切にし、既にある解についてはそれを紹介するに留め、あまり独自の論を展開することは多くない。自説を出すときも控えめな表現が多く、この点が山田先生らしさを感じるところである。
小樽に関して山田氏が独自に出した地名解は、於古発の「ウコパシ(急流が走り寄る)」、色内の「エンルムナイ(岬の川)」、有幌の「ハルポロ(食糧多き処)」、勝内の「ヘロキアッナイ(鰊の群来る川)」、星置の「ペシポキ(崖の下)」などがあるが、個人的には同意しがたい案である。
更科源蔵
詩人でありアイヌに関する多くの詩集や伝説集などを残した。更科源蔵氏の『アイヌ語地名解 北海道の地名の起源』は多くの道内の多くの地名の由来を比較的簡潔に解説している。『北海道 駅名の起源』の編纂にも加わっており、氏の地名解がそのまま用いられていることも少なくない。とりわけ小樽を「オタ・オル・ナイ」と初めて解したのは更科氏だと思われる。
他に小樽に関する更科源蔵氏の独自解には、勝納の「水源沢」、蘭島の「下り坂の後ろにある川」、塩谷の「岩礁の多い海岸」、朝里の「砂浜沿いの草原」、桃内の「つまる川」などがある。
榊原正文
榊原氏の『データベースアイヌ語地名』シリーズは細かい支流に至るまで非常に詳細に考察しており、山田氏や更科氏も取り上げていないような地名にも深く切り込んでいる。地名研究をする上では欠かせない本である。
榊原氏独自の解釈としては、畚部、蘭島、於古発、茅柴、兜岬などに見られる。
第四世代(現代)
ネイティブなアイヌ語話者もほぼいなくなり、当時を知る古老ももう居ない。しかし地名研究はむしろ加速しており、それに携わる人は多い。インターネットのおかげで、膨大な情報を個人が簡単に得ることができるようになり、それを発表する機会も増えた。それゆえに地名解も玉石混交状態ではある。
この世代の地名研究の強みは、いかに多くの裏付け情報を基にして考察できるかに掛かっている。
江戸時代のあらゆる日誌や地図や文献に目を通し、比較して検討しなくてはならない。また単に辞書から単語を拾い上げるだけでなく、アイヌ語の文法を正確に捕らえて記述しなくてはならない。そういう意味ではハードルの高くなった研究と言えるかもしれない。
しかし、大変面白い研究でもある。まだまだ誰も正解にたどり着いていない地名はたくさんある。その意味を見つけ出して、論証するのはとても楽しい研究だ。自分もまだまだ若輩者で学び始めたばかりであるが、それを一つ一つ解き明かしていきたいと思っている。
→小樽のアイヌ語地名解(随時更新中)
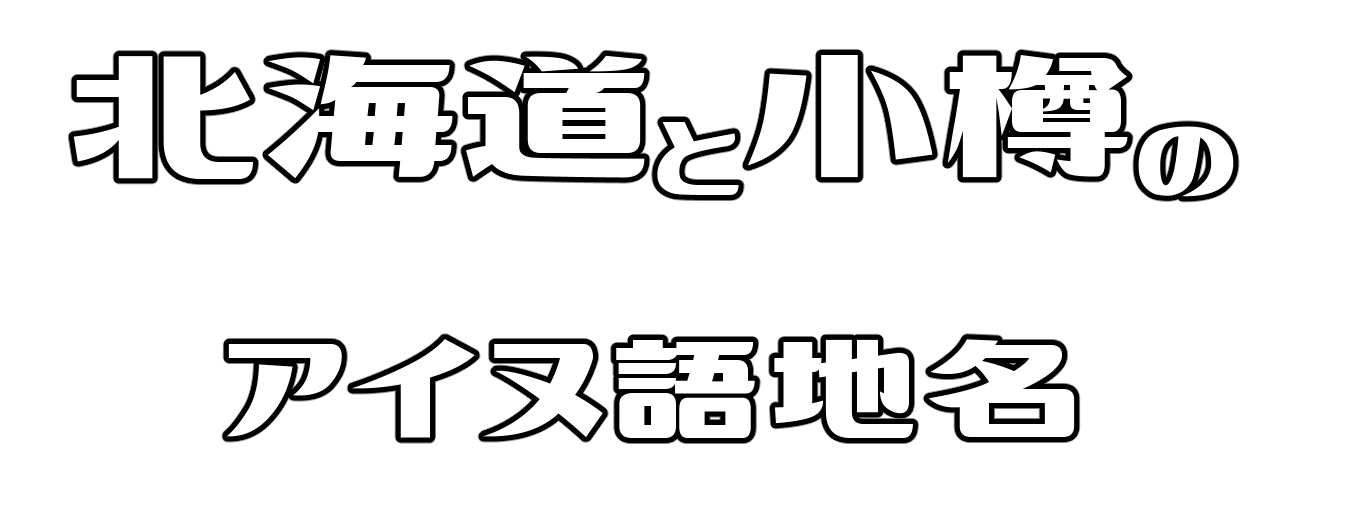
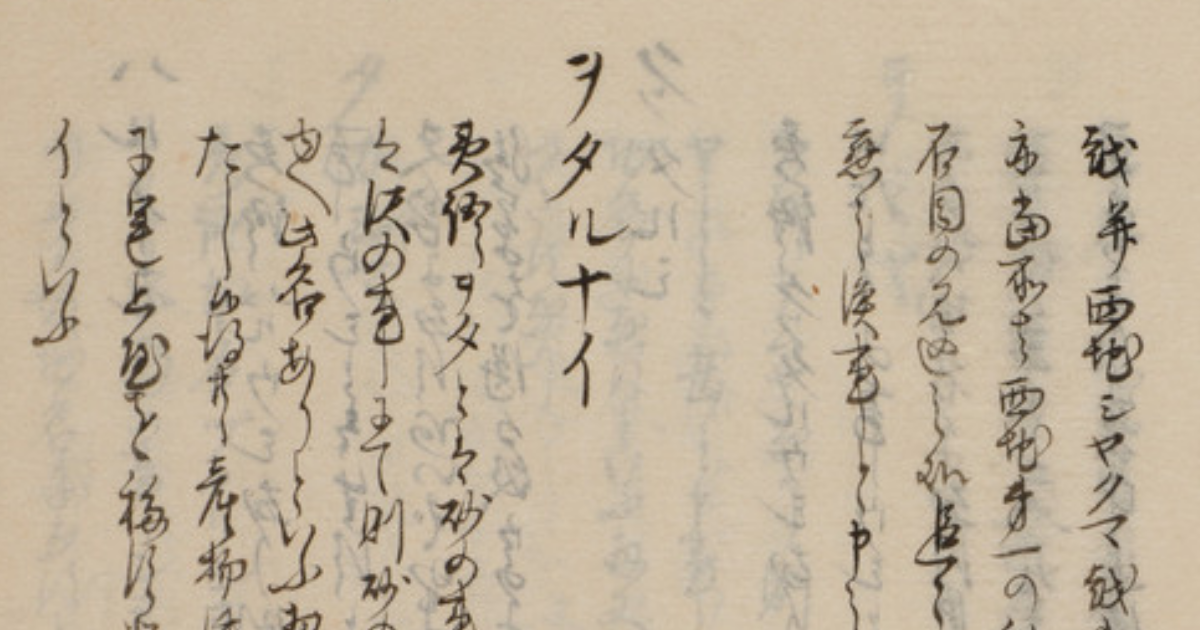


コメント