 地名の由来
地名の由来 誰も知らない札幌の由来を考える
サッポロの由来は誰も知らない地名の由来は面白い北海道の地名の多くはアイヌ語由来になっている。たとえば積丹しゃこたんは〈夏の集落〉だとか、富良野ふらのは〈匂いがする所〉だとか、美瑛びえいは〈白みがかった所〉だとか。そう言われてみると、脳裏に夏...
 地名の由来
地名の由来  地名の由来
地名の由来  地名の由来
地名の由来 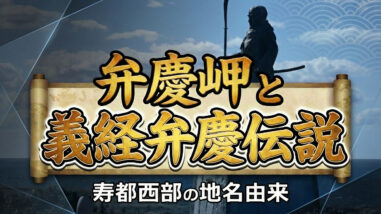 地名の由来
地名の由来 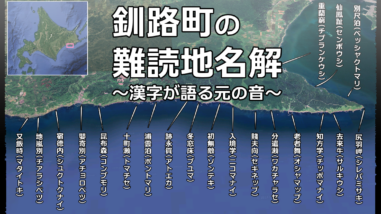 地名の由来
地名の由来 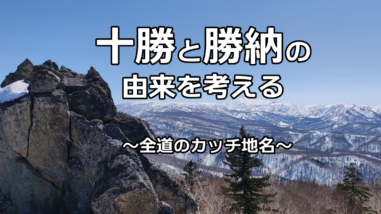 地名の由来
地名の由来  地名の由来
地名の由来 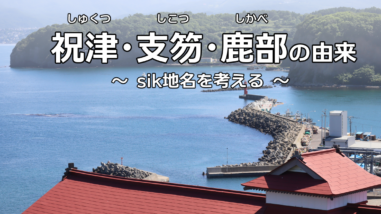 地名の由来
地名の由来 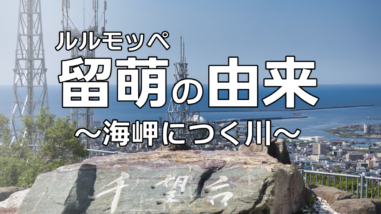 地名の由来
地名の由来  地名の由来
地名の由来 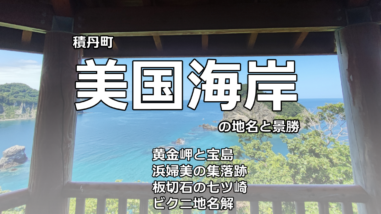 地名の由来
地名の由来 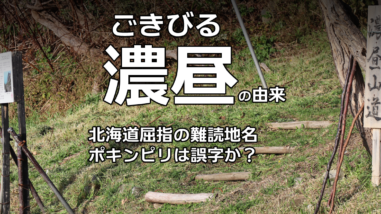 地名の由来
地名の由来 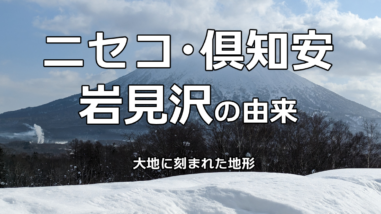 地名の由来
地名の由来 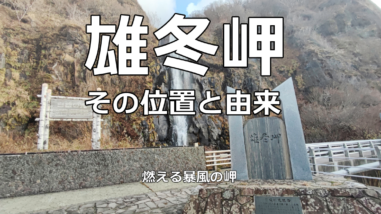 地名の由来
地名の由来  地名の由来
地名の由来  地名の由来
地名の由来  地名の由来
地名の由来  地名の由来
地名の由来  地名の由来
地名の由来 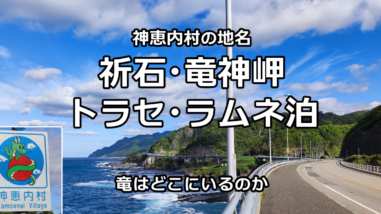 地名の由来
地名の由来  地名の由来
地名の由来 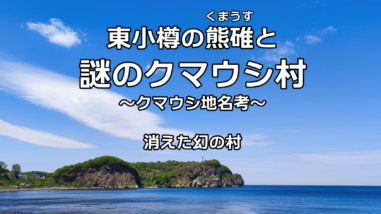 地名の由来
地名の由来  地名の由来
地名の由来  地名の由来
地名の由来 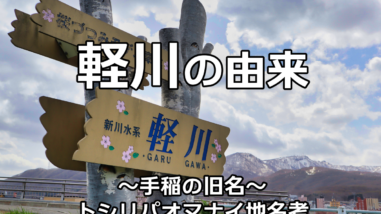 地名の由来
地名の由来  地名の由来
地名の由来 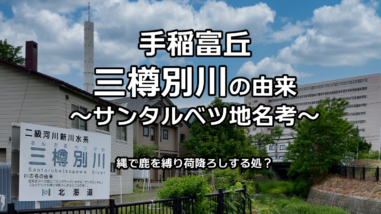 地名の由来
地名の由来  地名の由来
地名の由来  地名の由来
地名の由来  地名の由来
地名の由来  地名の由来
地名の由来  地名の由来
地名の由来  地名の由来
地名の由来